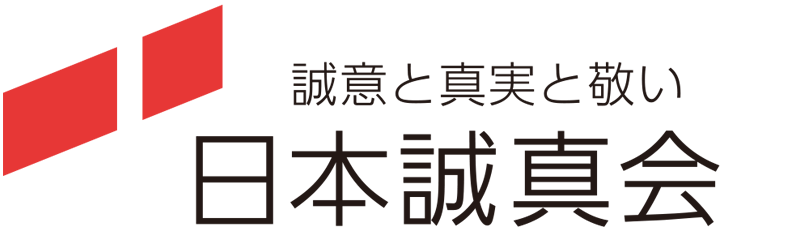令和7年3月20日
日本誠真会
顧問(憲法学会会員、弁護士)南出 喜久治
1 はじめに
⑴ 日本誠真会の党員規約の前文には、「日本誠真会は、現代日本が真の独立国家とは言い難い状況にあるという認識から出発しています。その根底にあるのは、二つの重要な問題点です。
第一に、現行の日本国憲法は、占領下においてGHQによって起草されたものであり、その後の日本の主権回復後も、あたかもそれが正当な憲法であるかのように国民に認識され、あたかも呪縛のように機能し続けているという事実です。これは、独立国家としての自主性を著しく損なう要因となっています。
第二に、エネルギーと食糧の自給率の低さです。国家の根幹を支えるべきこの二つの要素を海外に大きく依存している現状は、真の意味での独立を阻害しています。あたかも見えざる鎖で繋がれた属国のような状態が、政策レベルで継続されていると言わざるを得ません。
日本誠真会は、この二つの「属国体制」、すなわち占領憲法体制とエネルギー・食糧依存体制からの脱却こそが、日本の完全な独立を達成するための最重要課題であると考えます。これこそが、私たちの活動の原点であり、あらゆる政策の基盤となります。」とあります。
⑵ そして、これに基づいて、日本誠真会のホームページの「はじめに」の冒頭には、「日本誠真会が指摘する「日本の病」とは、すなわち「属国病」であり、その根本的な原因は、憲法とエネルギーの2つの領域における依存体質に集約されます。現代日本は、占領下で制定された憲法と、海外依存に基づくエネルギー・食糧供給という二重の問題により、国家としての自主性が著しく損なわれています。
以下、その問題点と解決策について、真正護憲論の視点とエネルギー自給自立の必要性を踏まえ、具体的な提言を示します。」として、まず、【憲法問題と真正護憲論】として、「現行の日本国憲法(占領憲法)は、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印から始まるGHQの完全軍事占領による非独立状態において起草されたものであり、主権国家が制定する正当な憲法としては到底認められません。
これは、我が国の歴史的な法的伝統に基づく古来より伝承されてきた祖法とは程遠い異形のものであり、制定法としては祖法を継承した大日本帝国憲法(帝国憲法)が正統なものであるという認識に立っています。
従来、占領憲法を完全に無効とする無効論も唱えられてきましたが、その立場は、占領憲法下でなされたすべての法令、行政処分、判決、ひいては国会、内閣、司法などの国家機関のすべてや公務員の地位までもことごとく否定するという、極めて革命的かつ破壊的な見解です。
我が国は「法的安定性」を重んじ、平穏な解消を国是としているため、急激な制度破壊は到底相応しいものではありません。真正護憲論は、これまでの無効論とは異なり、法的安定性への配慮を基本とし、占領憲法が帝国憲法第73条及び第75条に違反したものであることから、憲法としては無効であるとした上で、帝国憲法第76条第1項の無効規範の転換理論によって、サンフランシスコ講和条約の発効によって占領期が終了して「半独立」が実現するまでの間の中間地点で成立した講和条約(東京条約)としての限度で効力を認めますので法的安定性を損なうことはありません。
つまり、帝国憲法は今も現存しており、その下に占領憲法という講和条約が存在するのであり、この条約を連合国に向かって破棄通告をした上で真の独立宣言を行い帝国憲法の復元改正を熟慮の上で実現しようとするものです。
石原慎太郎氏が東京都知事時代の平成24年4月にワシントンで占領憲法の破棄通告を訴えたのもこの真正護憲論の考えによるものであり、石原氏の遺志を受け継いてさらに発展させ真の独立を実現できる唯一の政党が日本誠真会なのです。」として真正護憲論の概要が説明されていますが、本書では、この真正護憲論について、以下においてもう少し詳しく解説することにします。
⑶ 真正護憲論とは、GHQの完全軍事占領下にあった非独立状態の我が国が制定したとする日本国憲法と称するもの(占領憲法)は、主権国家の憲法ではなく、そもそも無効のものであるとすることについて、国法学、憲法学の観点から確立された理論です。
⑷ 真正なる我が国の成文憲法は、大日本帝国憲法(帝国憲法)であって、いまも憲法として正統に現存しているものであり、それを護憲するために、貴族院、枢密院などの欠損している機関やその他現在では不備等のある規定を正当な手続によって適正なものに改正して現代に適合する憲法改正を実現すべきであるとする原状回復論に基づいて「復元改正」を成し遂げて国家の基本秩序を再生する必要があるのです。
⑸ つまり、真正護憲論の骨子は、占領憲法は憲法としては無効であり、ポツダム宣言受諾と降伏文書の調印によって始まった非独立占領期間の長いトンネルの入口を経て、サンフランシスコ講和条約によって半独立となった出口との中間の地点に存在する「東京条約」と看做されるとの見解なのです。
⑹ 以下においては、真正護憲論の論拠となる条項や事実等を示した上で、その解説を※印で行います。
2 日本国憲法(占領憲法)の無効性
⑴ 帝國憲法違反
① 第73条「將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ」
※ マッカーサー憲法草案の交付が実質的な発議であり、天皇の勅命は形骸化したものであって、発議大権が簒奪されたことになり無効である。
② 第75条「憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス」
※ 摂政が置かれるのは、天皇が御不例などにより天皇が自らの意志で統治権を総覧することが不可能な事態であるが、それは予測しうる国家における「通常の変局時」(伊藤博文『憲法義解』)である。しかし、我が国がバーンズ回答と降伏文書にある「subject to(隷属下)」に置かれて天皇自らが大権を一切行使できないという国家の「異常な変局時」に憲法及び典範が改正できないというのは当然であり「勿論解釈」によるものである。
③ 上諭「將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ」
※ 憲法改正というのは、各条毎に個別に改正するものであって、どの条項がどの条項で改正されたのかの対応関係が不明な全面改正は、改正として無効である上に、このような全面改正は「敢テ之カ紛更ヲ試ミルコト」に該当する。
④ 帝國議会では、天皇の発議に対して賛否を行うだけで、発議案の修正ができないとされていたが、衆議院で2回、貴族院で1回改正されたので、これは帝國憲法第73条に違反する。
※ 帝國議会で改正できないのは、これを許せば、天皇の発議に藉口して様々な改正条項を修正することができることになり天皇の発議権を簒奪することになるとして、当時のほぼすべての憲法学者の定説であった。そのことを帝國議会で衆議院議員野坂参三が指摘したのであり、日本共産党は今とは違って占領憲法無効論だったので、改正に反対した。
⑵ 国際公法違反
① ハーグ条約の条約付属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則』第43条(占領地の法律の尊重)「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ」
※ ポツダム宣言第10項には、大正デモクラシーなどの「民主主義的傾向の復活強化(revival and strengthening)」を求めていたのであって、帝國憲法下での対応は充分可能であったことから「絶対的ノ支障」は全くなかった。
② フランス1946年憲法第94条「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続も、着手され、または遂行されることはできない。」(ヴィシー政権のペタン憲法の無効化)
※ 東西分裂時代の西ドイツにおいて、「ドイツ連邦共和国基本法」(ボン基本法)が制定された際、「憲法(Verfassung)」ではなく、あくまでも暫定的な「基本法(Grundgesetz)」であるとされたのはこの考えによるものである。
⑶ 革命憲法説(8月革命説)の破綻
① 非独立軍事占領下では国家主権は存在しないので、主権国家の根本規範である憲法を制定することは不可能である。
② 主権国家内での国民の自主的、主体的な政治変革を革命というのであって、「subject to(隷属下)」で主権を喪失した軍事占領下では革命が起こるはずがない。
③ 主権喪失下において主権の発動としての革命が起こり、憲法が制定できるとするのは形容矛盾である。
④ 昭和20年8月以降に国民の自主的、主体的な革命的政治変革はなかった。
⑤ 公布文「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
※ 占領憲法は、帝國憲法第73条による手続を経て改正された改正法であると宣言されており、革命によって憲法が制定されたとはされていない。
⑷ 承詔必謹論の破綻
① 天皇の公布行為は事実行為であり、公布は規範制定行為ではない。
② 無効の憲法を天皇の公布行為を根拠として有効とすることは天皇主権に陥る。
③ 帝國憲法第4条は、「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」とあり、帝國憲法は天皇主権ではなく、立憲君主制の憲法なのである。
3 占領憲法の効力
⑴ 無効規範の転換
① 帝國憲法第76条第1項「法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス」
② 「憲法」ではなく実質的には「東京条約」なのである。
③ 「何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス」というのは、平易に言えば、「ラーメン大学」といふ名前のラーメン屋は「大学」ではなく、やはり「ラーメン屋」なのであつて、ラーメン屋の限度で認められるべきであるということである。
④ 占領憲法は憲法としては無効であるが、帝國憲法下の講和条約(東京条約)の限度で認められる。
※ マッカーサー憲法草案を帝國議会が秘密会において翻訳作業を行って英文と邦文の文言の修正を行い、その成文についてGHQの承認を得て帝國議会で形式的な改正会議を経て、英文官報と邦文官報の双方に掲載されて確定した。
※ マッカーサーの初めの指令は、占領期における公用語を英語とするとして、日本語は公用語ではなくなった。そのために、占領期間中は英文官報が正式公報として発行された。それゆえ、帝國議会で成立したとする邦文の「日本国憲法」は正式な憲法ではなく、英文官報に掲載された「THE CONSTITUTION OF JAPAN」が正式な占領憲法なのであり、邦文「日本国憲法」はその訳文に過ぎない。
※ その成立過程は、昭和21年2月13日にGHQから我が国に指令された英文の「日本国憲法草案」(GHQ草案)を翻訳したものを帝國議会に提案され、法律専門家等の見解の聴取もせずに直ちに委員会付託となり、これを秘密会として、そこでの作業は、GHQ草案と政府原案を比較して、英文と邦文との対比表現、逐条解釈、字句の選定と訂正、各条項の意義と各条項間の整合性などの検討をするだけの単なる「翻訳委員会」にすぎず、GHQに対してその経過報告をして了解を受ける手続については、ポツダム宣言受諾直後の昭和20年8月19日、マニラに派遣された河邊虎四郎全権がGHQとの「マニラ会談」においてGHQから手交され要求事項に基づいて外務省が設置した「終戦連絡事務局」を通じてGHQの承認を必要とされた。この終戦連絡事務局というのは、「大東亜戦争終結ニ関シ帝國ト戦争状態ニ在リタル諸外国ノ官憲トノ連絡ニ関スル事項ヲ掌ル」というものであり、その後に名称等が変更されたものの、ポツダム宣言受諾の直後からサンフランシスコ講和条約発効までの非独立時代に一貫して存続してきた組織である。それは、占領憲法の施行の前後においても全く変はることはなかった。つまり、占領憲法の制定、施行という形式手続とは全く無関係に一貫した講和交渉の窓口であって、まさに占領憲法は講和条約と看做される実質があったのである
⑵ 交戦権の意味
① 「国の交戦権は、これを認めない。」とある。「占領憲法第9条第2項後段の交戦権」(The right of belligerency)とは、「アメリカ連邦憲法の大統領と連邦議会に分有する戦争権限」(war powers)のことであり、「帝國憲法第11条(統帥大権)及び第13条(宣戦大権、講和大権)の戦争大権」のことであって、交戦権とは、戦争大権に含まれる権限の一つである。
② 占領憲法に自主性があれば、「わが国は交戦権を放棄する」と規定するのであるが、「認めない」ということになっているのは、その認めないとする主体は、GHQであり、これは、「(GHQは)日本国の交戦権を認めない」といふ実質的な講和条約であったことになる。
⑶ 講和条約
① ポツダム宣言の受諾及び降伏文書の調印は、帝國憲法第13条の講和大権の発動によるものである。
② 我が国は、ポツダム宣言の受諾(昭和20年8月14日)及び降伏文書の調印(同年9月2日)といふ講和条約を「入口条約」として、昭和27年4月28日に発効して戦争状態が終結したサンフランシスコ講和条約を「出口条約」として、その間の非独立占領の長いトンネルを抜けて、ようやく半独立的の地位を得た。そして、そのトンネルの中間に占領憲法という「中間条約」が存在するのである。
③ しかし、非独立時代の占領憲法第73条第3号の条約締結権は交戦権(講和大権)がないので一般条約締結権限に過ぎず講和条約締結権はない。
④ 帝國憲法第13条は、「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」とし、宣戦大権、講和大権である戦争権限(交戦権)と一般の条約大権とは明確に区別されており、占領憲法第73条第3号の条約締結権には、戦争大権(交戦権)が含まれないことは明らかなのである。
⑤ つまり、帝國憲法が現存していたために我が国は講和独立、戦争状態を終了させることができたのである。
⑷ 「戦争状態」の終結と破棄
① 「戦争状態」の終結(昭和26年のサンフランシスコ平和条約、同年の日華平和条約、昭和31年の日ソ共同宣言、昭和47年の日中共同声明)は、講和大権(交戦権)が認められていない占領憲法ですることは不可能である。
② 昭和47年の大平外相による日華平和条約の破棄通告は、一旦終結させた戦争状態を復活(宣戦行為)となり、交戦権の行使となるので占領憲法ではできない。
③ 結局、帝國憲法が現存していたために、戦争大権と属する講和大権を行使して戦争状態を終結したり、その破棄通告をしたりすることができたのである。
⑸ 自衛権と自衛戦争権限の区別
① GHQ占領下で制定した占領憲法に自衛権が認められるはずがない。
② 占領下でわが国の自衛権を認めるというのは、武力による独立権をみとめることとなるので、占領軍がこれを認めるはずかない。
③ 仮に、占領憲法で自衛権が認められたとしても、それは警察力による排除、自警団等による民間防衛などに限られ、自衛隊によって敵国の攻撃に対して自衛戦争を行うことは、交戦権の行使となるので禁じられることになる。
④ 自衛隊の権限は、警察官職務執行法上の警察権限しかなく、自衛官は、軍服を着たコスプレ警察官である。正当防衛反撃しかできないのである。
⑤ しかし、占領憲法第9条第2項前段(前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。)からして、自衛隊は軍隊であるから違憲の存在である。
⑥ つまり、軍隊であるか否かは、軍としての名称が付けられているか否かではなく、近代戦争を遂行する人的組織と物的装備を備える実力組織が軍隊であり戦力であって、自衛隊は軍隊であって違憲の存在である。「自衛隊という呼称なので軍隊ではない」という詭弁は、「ラーメン大学」の類である。
⑦ ところが、真正護憲論では、自衛隊は帝國憲法下の皇軍(軍隊)であり、当然に合憲の存在と評価されるので、占領憲法の改正は不要であり有害無益である。
4 原状回復論(公理)
⑴ 昭和3年常設仲裁裁判所のパルマス島事件判決、人質救出、拉致問題解決などで適用されている公法上、私法上の原状回復法理が憲法問題においても適用される。
⑵ 拉致問題では、拉致された被害者が祖国に帰国して拉致前の状態に原状回復するのが問題解決のための前提として当然であると認められているのに、憲法問題では、一旦は帝國憲法に復元してから改正の議論をするべきであるとする原状回復論が適用されないのは大いなる矛盾である。
⑶ 帝國憲法の復元改正(復元とは規範意識の復元。帝國憲法は復元行為によらずとも現存していることの規範意識を復元すること)は、帝國憲法第8条の緊急勅令により占領統治が始まったので、復元改正手続でも、再び緊急勅令によって占領期の法制度の改変と清算(占領憲法無効宣言など)を行う。
⑷ 旧無効論のように、占領憲法を絶対無効であるとすると、これまで法律、裁判、行政処分等のすべてが無効となって、法的安定性を著しく害する革命状態となるので、このような無効論は排除されなければならない。そして、占領憲法が講和条約の限度で認められ、その国内的効力を肯定しつつ、時間をかけて慎重に帝國憲法の改正作業を行う必要がある。
⑸ 講和条約である占領憲法(東京条約)による拘束から逃れるためには、事情変更の原則により、連合国(アメリカ)に対して、講和条約の破棄通告をすれば足りる。国内的には、国会による無効確認決議または内閣総理大臣による無効確認宣言を行う。
※ 石原慎太郎元東京都知事は、真正護憲論に基づいて、平成24年4月16日にワシントンで、1時間をかけて占領憲法の破棄通告を告げることの話をして、最後の10分で尖閣諸島の東京都買取り案を表明したが、メディアは、占領憲法の破棄通告の話題を取り上げず、尖閣諸島の買取だけが話題となって独り歩きしてしまった。
⑹ そして、無効確認決議ないしは無効確認宣言を行った後に、憲法復元のために帝國憲法第8条の緊急勅令に基づき、占領憲法を暫定的な憲法代用法として認めた上で、戦後の法制度を根本的に見直して帝國憲法の改正作業に入る。
※ 昭和44年8月1日の岡山県奈義町における『大日本帝國憲法復原決議』と石原都知事によるワシントンでの占領憲法破棄通告に続いて憲法復元運動を国政の場で展開する必要がある。
5 参考法令
⑴ 大日本帝國憲法(明治22年2月11日公布、同23年11月29日施行)
第八条
天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ敕令ヲ發ス
此ノ敕令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ效力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十二条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第十三条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
第七十三条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
第七十四条 皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス
第七十五条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
第七十六条 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ效力ヲ有ス
歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ總テ第六十七條ノ例ニ依ル
⑵ THE CONSTITUTION OF JAPAN
(邦訳)日本国憲法(昭和21年11月3日公布、昭和22年5月3日施行)
Article 1.
The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることはできない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
⑶ サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)(昭和26年9月8日調印、昭和27年4月28日発効)
第一条
(a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第十一条
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基づく場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基づく場合の外、行使することができない。
第十九条
(a) 日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の効力発生の前の日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。
(b) 前記の放棄には、千九百三十九年九月一日からこの条約の効力発生までの間に日本国の船舶に関していずれかの連合国がとつた行動から生じた請求権並びに連合国の手中にある日本人捕虜及び被抑留者に関して生じた請求権及び債権が含まれる。但し、千九百四十五年九月二日以後いずれかの連合国が制定した法律で特に認められた日本人の請求権を含まない。
(c) 相互放棄を条件として、日本国政府は、また、政府間の請求権及び戦争中に受けた滅失又は損害に関する請求権を含むドイツ及びドイツ国民に対するすべての請求権(債権を含む。)を日本国政府及び日本国民のために放棄する。但し、(a)千九百三十九年九月一日前に締結された契約及び取得された権利に関する請求権並びに(b)千九百四十五年九月二日後に日本国とドイツとの間の貿易及び金融の関係から生じた請求権を除く。この放棄は、この条約の第十六条及び第二十条に従ってとられる行動を害するものではない。
(d) 日本国は、占領期間中に占領当局の指令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の法律によって許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。
第二十三条
(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によって批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
(b) この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。
⑷ 日華平和条約(昭和27年4月28日調印、同年8月5日発効)
第一条 日本国と中華民国との間の戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する。
⑸ 日ソ共同宣言(昭和31年10月19日調印、同年12月12日発効)
第一条 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
⑹ 日中共同声明(昭和47年9月29日)
一 日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。
⑺ 国際連合憲章(昭和20年6月26日署名、同年10月24日発効、昭和31年12月18日日本国加入効力発生、同月19日公布、条約第26号)
第五十三条
1 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基づいて又は地域的機関によってとられてはならない。もつとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第百七条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基づいてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界対戦中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であつた国に適用される。
第百七条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であつた国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
⑻ 「大日本帝國憲法復原決議」(岡山県奈義町議会・昭和44年7月30日提出、同年8月1日可決承認(贊成10名、反對7名)
地方自治法第百十二條に基き下記の議案を提出する。
昭和四十四年七月三十日
奈義町議會議長 青木守夫 殿
(議案) 大日本帝國憲法復原決議案
(提案者) 奈義町議會議員(森安巌、吉元義秋、野々上昇、關場光士、鷹取巌、畝原三好、岡正章、有元康雄)
(提案理由)
私達は下記の理由と目的により大日本帝國憲法復原決議案を提出いたします。
現行日本國憲法は、その内容に於して全く戰勝國が占領目的遂行のため、假に憲法と稱する行政管理基本法にすぎないものであることは、議員各位既に御承知の通りであります。(以下省略)